「バイオマスツアー真庭」が新エネ大賞を受賞しました
2009年12月24日、岡山県真庭地域のバイオマス利活用の実態を見て、触れて、学べる バイオマスツアー真庭が、経済産業省の 第14回 新エネ大賞 において金賞の 経済産業大臣賞を受賞しました!
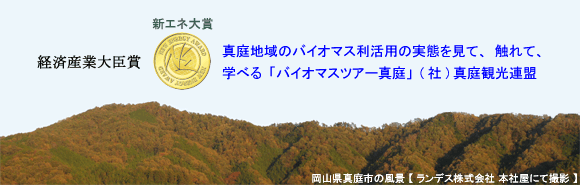
「バイオマス」とは
バイオマスとは、生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼びます。
再生可能なバイオマスとしては木屑、紙屑、生ごみ、家畜の糞尿、下水汚泥など、身近にたくさんあります。
「バイオマスツアー真庭」とは
岡山県の北部に位置し、古より豊かな森と自然の恩恵に育まれてきた「真庭」では、バイオマス事業への取り組みが盛んに行なわれています。
真庭のバイオマス事業は、身近な生物資源を再利用するという技術的な側面からとらえるだけでなく、その技術を基盤に長い歴史の営みの延長線上に、地域完結型のCO2を増加させない暮らしを実現することを最大の目的としています。農業、林業、工業、商業、教育、福祉、技や文化など人間の生活のすべてが、バイオマス事業という持続可能な産業の輪の中で繋がる地域をめざして研究、実践が重ねられています。
「バイオマスツアー真庭」とは、自然と共存し伝統を守りながら人々が生活するバイオマスタウン「真庭」を視察する有料のバスツアーで、北海道から沖縄まで年間2000人を超える参加者があります。
ツアー内容は、新エネルギー利用施設の見学だけでなく、地球環境問題や森林教室、生き物観察会、バイオマスタウン学習、野菜収穫体験など、市内観光地を環境、自然、バイオマスという観点からストーリー創りが行なわれ、親子体験や環境学習、地元高校生がガイド役を務める見学会など企画性の高いものとなっています。
ランデス株式会社とバイオマスツアーとの係わり
ランデス株式会社は、「バイオマスツアー真庭」視察コースの1つとなっており、真庭の製材所や森林から出る間伐材や端材を原料として加工した「木片コンクリート(MOCO)」の製品展示および紹介を行なっております。



ちなみに、この「木片コンクリート」。2009年12月に「第2回真庭ブランド」として認定されました!

バイオマスツアーの内容と参加方法
バイオマスツアーでは、バイオマス事業の一連の循環を網羅した1泊2日コース(A)、
林業中心の1泊2日コース(B)、短時間日帰りコース(C)の
3つのコースが用意されています。
真庭のバイオマス事業に興味をお持ちの方は、
ぜひバスツアーを体験されてはいかがでしょうか?
ツアーへのお申込み方法、代金の確認、ご質問は、
バイオマスツアー真庭公式HPをご確認いただき、
真庭観光連盟バイオマスツアー係までお問合せください。
営業イチ押し
2分割ボックスカルバートを使って道路拡幅 のご紹介
技術情報
2026年02月16日
2025年11月13日
港湾工事における“新技術カタログ”(テーマ3:藻場・干潟造成)に掲載されました!
2025年10月01日
第19回ミリタリーエンジニアテクノフェア2025 に出展しました!
2025年09月11日
2025年09月01日
CUCOコンクリートランデス実績(神戸市大型張りブロック)がCUCOホームページに掲載されました。(外部リンク)
新着情報
2025年11月28日
2025年08月08日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2025」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2025年06月02日
脱炭素化への取組みとして久米南工場に太陽光発電設備を設置しました!※年間CO2排出削減効果:杉の木約12, 000本の吸収量に相当!(外部リンク)
2025年03月12日
広島大学・大学院の学生の皆様が視察に来社されました!(PDFリンク)
2025年03月01日
「はんざきブロック」が毎日小学生新聞で取り上げられました!(外部リンク)


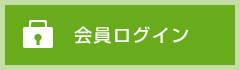
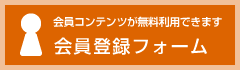
「新エネ大賞」とは、新エネルギーの一層の導入推進と普及および啓発を図るため、新エネルギーに係る商品および新エネルギーの導入、あるいは普及啓発活動を広く募集し、そのうち優れたものを表彰するものです。
バイオマス事業による地域づくりをテーマとしてバスツアーによる産業観光の創出を図るとともに地域振興に貢献している。環境教育に係わる企画ツアーなどのメニューもあり、視察に訪れる人も年々増加している。地域内循環社会の構築に向けた取り組みは、他地域への模範的な事例となることが高く評価された。